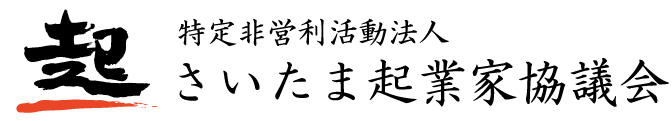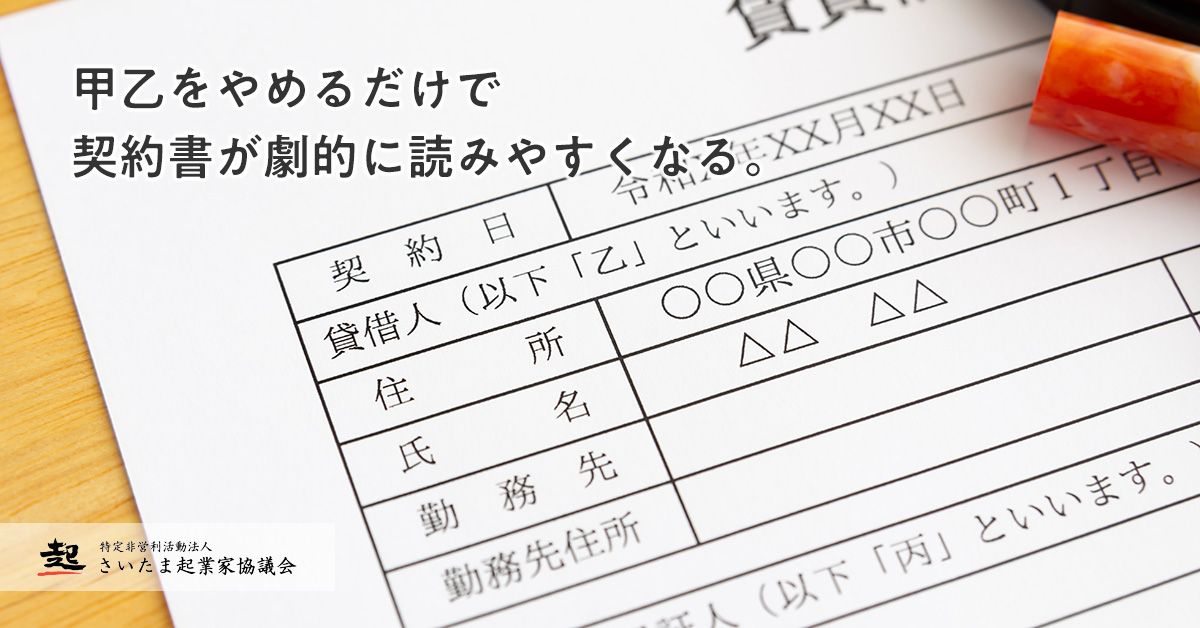
甲乙をやめるだけで契約書が劇的に読みやすくなる
起業家の皆さま、
「契約書って大事なのは分かっているんだけど、難しくて読む気が失せる」
と感じたことはありませんか?
今回は、「契約書が劇的に読みやすくなる方法」について、私の経験上からのアドバイスさせていただきたいと思います。
何より、そんな私自身、契約書に関する仕事にかかわるようになった当初は、
「契約書は同じ日本語で書かれているはずなのに、小説と違ってなんで頭にスッと入ってこなのだろう」
そんなことを思いながら契約書と格闘していました。
小説と契約書の差は何か?
それはリアリティの差なのではないかと気づきました。
小説は、登場人物それぞれが具体的な言葉を発して物語を展開してきます。
ですので、文字だけでもリアリティを感じ、どんどん想像が膨らみ、スッと頭に入ってきます。
一方、契約書はぱっと見無味乾燥な言葉が並べられています。
私自身たくさんの契約書に目を通していく中で、あることに気がつきました。
それは、
「契約書は目の前で行われているビジネスのことを文書に落とし込んだもの」
ということ。
契約書は自社と相手方との商売上の物語が書かれたものともいえます。
ですから、本来であれば、小説と同様、リアリティを感じ、感情移入して読み込んでいかなければ、契約書に仕掛けられている大きな罠に気づけないかもしれないのです。
その感情移入するためにはどのようにしたらよいか?自分なりに考えたところ、
「登場人物を具体的なものにしてみたらどうか」
ということを思いつきました。
つまり、契約書では「甲」「乙」で書かれてることの多い主語を、「当社」「お客様」あるいは具体的な会社名に変更してみたらしてみたらどうかということです。
契約書が電子データであれば、ワープロソフトの置換の機能を使うことによってあっという間に主語を変換することが可能です。
主語を変更し契約書上の登場人物を具体的なものとしたところ、劇的に読みやすくなり、頭にスッと入ってくるようになりました。
契約書では、例えば「○✕△株式会社」と正式名称を何度も書かなくて済むように、略して「甲」「乙」とすることが多いのはご承知のことと思います。
自社と相手方の正式名称が何度も何度も出てくる契約書は非常に読みにくい。
ですので、略称を用いるメリットはあります。
しかし、略称に「甲」「乙」を用いてしまうと、人ごとに思えて「リアリティ」を感じず、感情移入もできないという方も多いのではないでしょうか。
しかも、契約書を読み込んでいる途中で、「甲」「乙」どちらが自社のことなのか分からなくなって、あやうく意味を取り違えるところだったという、冷や汗をかいた経験をされた方は私だけではないはずです。
「契約書で略称を使うときには甲乙を使わなければならない」などと法律で決まっているわけではありません。
甲乙の略称表記をやめるという、ちょっとした工夫で、契約書は劇的に読みやすくなります。
私自身、契約書関係のセミナーの講師をさせていただく機会もあるのですが、上記エピソードとともにこの裏ワザを説明させていただくと、「目から鱗が落ちた」といったポジティブな感想をいただくことが多いので、今回コラムとしてまとめさせていただきました。
ぜひ試しにやってみてください!