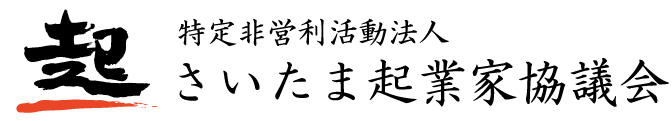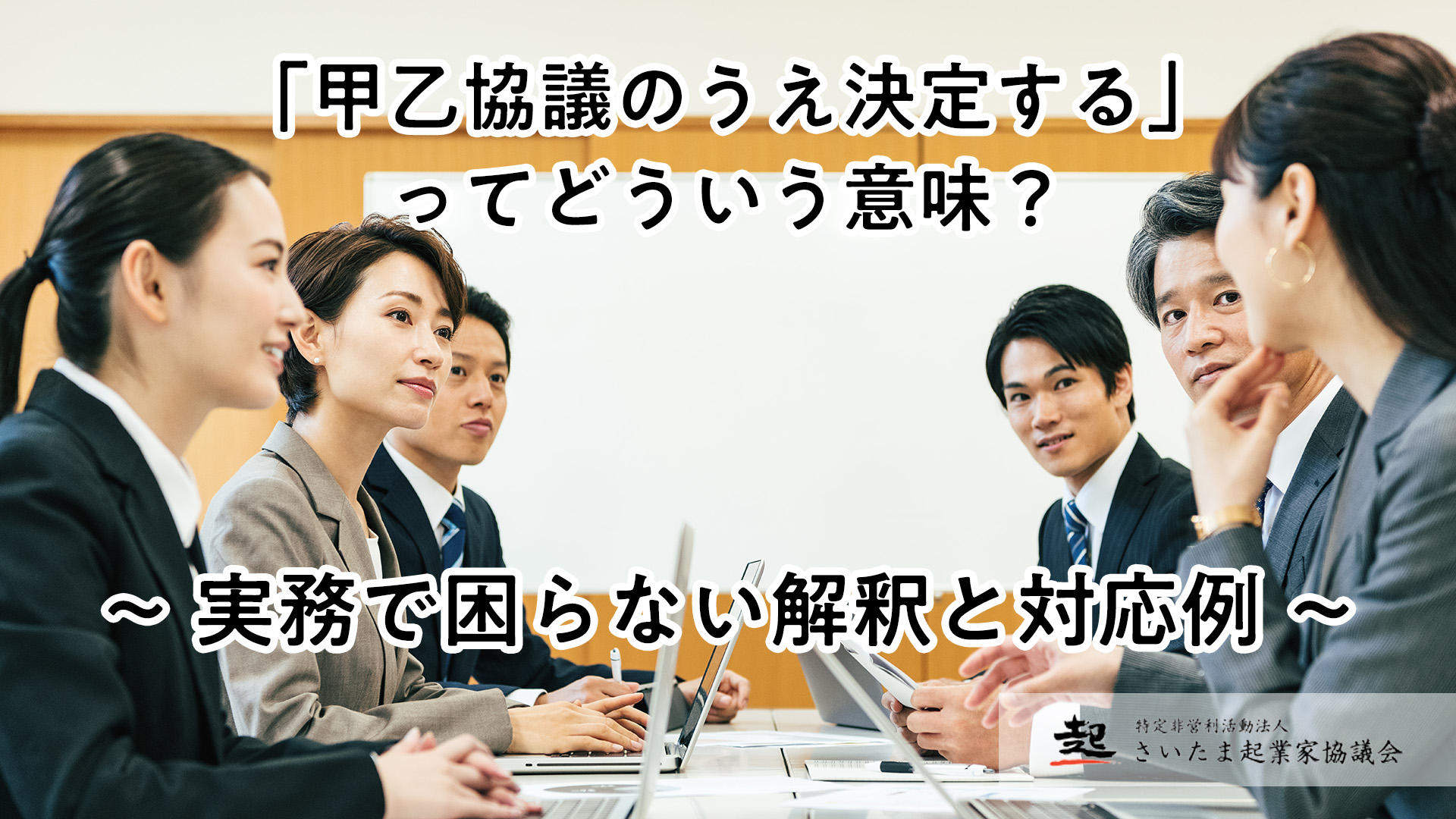
「甲乙協議のうえ決定する」ってどういう意味?~実務で困らない解釈と対応例
1.はじめに
契約書を読み慣れていない人でも、「協議のうえ決定する」という表現を目にしたことがあると思います。
取引条件の変更やイレギュラーな対応を想定して、契約書の中に自然に登場するフレーズです。
一見すると、柔軟で穏当な書き方ですが、いざトラブルが起きたとき、
「協議って、どこまでやればいいの?」
「相手が納得しなかったら契約違反になるの?」
といった疑問に直面することもあります。
この記事では、そんな協議条項の意味と限界、実務での対応例、そして契約条文の工夫ポイントまで、起業家の視点で丁寧に解説していきます。
2.「協議のうえ決定する」の基本構造と狙い
「協議のうえ決定する」という条文は、実務では次のような場面でよく使われます。
- 取引の諸条件が契約時点では確定していないとき
- 不測の事態への対応に関するとき
- 詳細を契約書にすべて書ききれないとき
たとえば以下のような記載です。
第○条(仕様の変更)
本契約の履行にあたり、やむを得ない事情が生じた場合には、甲乙協議のうえ、仕様の内容を変更することができる。
この表現は、契約時点では想定しきれない将来の状況に備えて、柔軟に対応する余地を残すためのものです。
しかし、表現が曖昧なぶん、対応のしかたを間違えるとトラブルに発展しかねません。
Sponsored 広告
3.法的にはどうなの?〜協議義務と合意義務は違う
「協議」とは、法的には「話し合いましょう」という意味にすぎません。
つまり、契約上「協議する」と定められていても、それは「合意する」ことまでを義務づけたものではないということです。
「協議条項」の実体
- 「誠実に協議の場を設ける」ことが求められる
- ただし、「合意しなければならない」義務ではない
- 協議の申し出を一方的に無視する、あるいは門前払いするような行為は、信義則に反するおそれあり
つまり、協議は「努力義務」のような位置づけです。
話し合いの場には応じなければならないが、無理に折れる必要はありません。
4.「嫌です」と言ったら違反?〜協議対応の実務ライン
契約書に「協議のうえ決定する」と書いてあるのに、相手の申し出を断ったら契約違反になるのでしょうか?
答えはNOです。
重要なのは「誠実に話し合いの場に応じたかどうか」であり、相手の提案を丸のみする必要はありません。
実務対応のステップ
- 協議の要請を受けたら、内容確認を依頼する
→「貴社のご提案の詳細について、趣旨をご教示ください」など。 - 社内で検討した結果を文書で回答する
→「社内関係者とも協議しましたが、今回は見送りたいと考えております」など。 - 結論は明確かつ丁寧に伝える
→「今回はご要望に沿えず恐縮ですが、今後ともよろしくお願いいたします。」
このような対応を取っていれば、協議義務は十分に果たしたと判断されます。
ポイントは、形式ではなく実質的な対応と、やり取りの記録を残すことです。
5.「協議条項」がトラブルの火種になることも
「協議のうえ決定する」といった表現は、柔軟な話し合いを促す意図で盛り込まれることが多いものの、実際の取引現場では、その文言を盾にして相手が拒絶姿勢をとる、あるいはこちらが慎重になりすぎて動きづらくなるというケースがあります。
ケース:価格改定を申し入れたが「協議していない」と反発された
長年続けてきた取引の中で、仕入価格や人件費の高騰を受けて、取引価格の見直しを申し入れたとします。ところが契約書には、「価格改定については甲乙協議のうえ決定する」と明記されており、相手方からは、
「協議もせずに一方的に値上げを通告するのは、契約違反だ!」
と強い反発を受けました。
実際には、何度か価格改定の必要性を伝え、資料を添えて説明も行っていたものの、相手からは「社内で検討中」といった返答が続き、協議が一向に進まない状況が続いていました。
やむを得ず、価格改定の通知を出したところ、このような反応を招いてしまったのです。
教訓:協議の経過を「記録として残す」ことが鍵
このような場合でも、実際に協議の機会を設けていたこと、そして誠実に対応していたことが明確に伝われば、「協議していない」との批判はかわすことができます。
重要なのは、その経過を客観的に示せるように記録を残しておくことです。
たとえば、以下のようなものです:
- 価格改定の提案メール
- 説明資料や根拠の送付履歴
- 協議日時の打診や経過報告
- 断られた経緯のメモや議事録
こうした履歴があれば、「誠実に協議を試みた」という姿勢が立証できます。
逆に、記録がなければ「一方的な通告だったのでは?」と疑われ、信頼を損ねるおそれもあります。
Sponsored 広告
6.トラブルを避けるための「書き方の工夫」
協議条項を使う場合は、次のような文言にアレンジしておくと、実務での混乱を防げることもあります。
アレンジ例1:協議期限を設ける
「甲乙協議のうえ決定する。ただし、協議開始後30日以内に合意に至らない場合は、甲の提案内容をもって決定する。」
→ 結論が出ないまま何ヶ月も保留、という事態を避けられます。
アレンジ例2:協議の対象範囲を限定する
「○○の変更については協議のうえ決定する。ただし、業務の継続に重大な支障が生じるおそれがあるときは、甲は単独で判断することができる。」
→ 無制限な協議義務から自社を守る設計が可能です。
アレンジ例3:協議不能時の処理方法をあらかじめ定める
「協議により解決できない場合は、甲乙いずれかの申し出により○○により決定する。」
→ 調停や仲裁などの第三者による判断、いずれかの当事者の責任者による決裁など、“最終判断のルール”があると安心です。
7.まとめ:「協議」は話し合いの“入口”にすぎない
- 協議条項は「話し合いをする」という努力義務にとどまり、「合意する」義務ではない
- 誠実に話し合い、記録を残しておけば、実務上も法的にも問題になりにくい
- 曖昧な条文のままだと、かえって意思決定を妨げるリスクがある
- 協議不調時のルールや期限を明記することで、事業判断のスピードを保てる
契約書に「協議する」と書かれているということは、いずれ協議せざるを得ない局面が訪れるかもしれないということでもあります。
だからこそ、「どこまで協議するのか」「協議できなかったときはどうするのか」まで見据えて契約書全体を設計していくが、起業家自身のリスクマネジメントになります。
“言った・言わない”ではなく、“書いてあった”を武器にできるのが契約書。
柔らかい言葉ほど、正確に扱う視点が大切です。